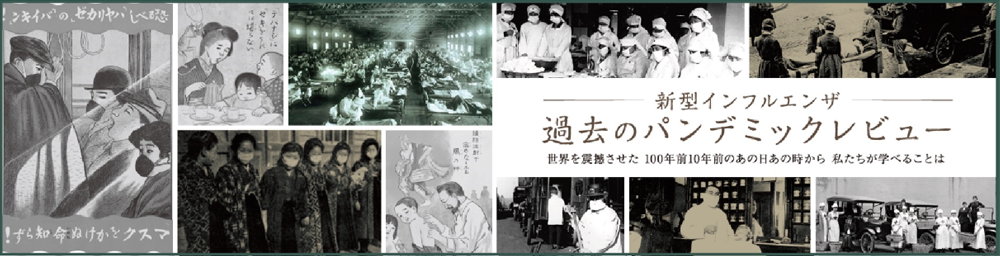
 2009年のパンデミックから10年の歩み(後半)
2009年のパンデミックから10年の歩み(後半)
国立保健医療科学院 健康危機管理研究部 上席主任研究官
齋藤 智也
はじめに
前回は国内の新型インフルエンザ対策の歴史と新しい法律、そしてそれに基づく政府行動計画についてご説明しました。続いては、特に医療・公衆衛生面の対策として、抗インフルエンザウイルス薬とインフルエンザワクチンの事前準備、そして訓練の話を書いてみたいと思います。
Ⅰ. 抗インフルエンザウイルス薬の備蓄と供給
かつて抗インフルエンザウイルス薬が市場に出回り始めた頃は、供給体制が十分ではなく、新型インフルエンザ発生時の需要急増による供給不安が懸念されました。その解決策として国や都道府県による抗インフルエンザウイルス薬の備蓄が開始されました。幸い2009年の新型インフルエンザ流行時にはその備蓄にほとんど手をつけることなく済みましたが、新型インフルエンザ発生時の需要の急増による薬剤の供給不安の問題には引き続き備える必要があります。
備えるためには何らかの目標が必要です。2009年のパンデミック以前から、全人口の25%が罹患する、との被害想定の下、諸外国における備蓄状況や医学的な知見に基づいて一定量の抗インフルエンザウイルス薬の備蓄が行われてきました。現在では、全ての罹患者の治療その他の医療対応に必要な量として、4,500万人分が備蓄目標とされています。国や都道府県が抗インフルエンザウイルス薬の備蓄を行うことは今も変わりませんが、変わったのは、季節毎に流行するインフルエンザに対する診療でも抗インフルエンザウイルス薬がより広く使われるようになり、市場流通量が増えたということ、また、日本の製薬企業が国内で製造する薬もあるため、即時生産や即時放出も可能になったということです。そのため、現在では、製薬企業や卸業者に保管されている薬が「流通備蓄」として1,000万人分あると見込んで、国や都道府県が備蓄するのは3,500万人分となっています。
もう一つの変化は、様々なタイプの抗インフルエンザウイルス薬が開発されてきたことです。どんな新型のウイルスが発生するかは分かりません。新型のウイルスが、準備していた薬に対して耐性(薬が効かない性質)を持っていて、備蓄していた薬の効果がなかった場合には、治療の選択肢が失われてしまいます。複数の抗インフルエンザウイルス薬を備蓄することで、使える薬が無い、という事態に直面するリスクを少なくすることができます。また、様々な年代の人にも使用できる薬を準備しておかなければなりません。そのため、多様性を持たせる観点から現在5種類の薬が備蓄の対象になっています。そのほか、現在では、特許の期限切れによりジェネリック医薬品も一部発売されています。どの薬をどれくらいの割合で備蓄するのかを、中長期的な視点でよく考えなければいけません。
備蓄とともに考えなければいけないのは供給戦略です。備蓄があっても、必要な時に届かなければ意味がありません。さらには、薬の種類が増えてくると、今後は、どの備蓄薬をどのような人に使っていくのか、時にはその優先順位も考えて、どのように効率的に配っていくかが問題になってきます。薬の備蓄を行うからには、供給するところまでを考えた綿密な戦略が欠かせないのです。
Ⅱ. ワクチンの備蓄と供給
インフルエンザワクチンは毎年みなさん打たれているでしょうか?例年、「今年は効く、効かない」といった話が議論になりますが、効くか効かぬか、と問われれば、インフルエンザワクチンは効く、といえます。ただ、はしかのワクチンのように、接種すればほぼ終生かかることはない、というほどの効果を期待するのであれば、それほどの期待には応えられません。効果を実感しにくいのも事実です。打たなくても罹らない人もいれば、打っていても罹る人もいます。また、インフルエンザには罹らなくてもそれ以外のウイルスなどによる似たような症状の風邪をひくことも多々あります。しかし、ワクチンを打った人は、ワクチンを打たない人に比べて、インフルエンザに感染して発病するリスクが減ることは様々な研究から明らかです。国内で毎年1,000万人から2,000万人もの患者が発生するインフルエンザですから、接種をした人の発病リスクが少しでも減らせれば社会全体として大きな意味があります。インフルエンザワクチンの製造には時間がかかります。インフルエンザウイルスは常に少しずつ顔つき(抗原性)が変化しています。そのため、毎年、その年に流行する可能性があるウイルスにより近い顔つきのウイルスを利用してワクチンを製造しており、流行期の約半年前から製造の準備を始めています。新型インフルエンザが発生すると、そのウイルスを入手し、それを元にして、ワクチンの素となる「ワクチン株」と呼ばれるウイルス株を作成します。このウイルス株を卵や培養細胞の中で増殖させたのち、複雑な工程を経て、ワクチンに必要な成分だけを抽出し、小分けして製品化し、国家検定を受け、ワクチンとして供給します。前回の2009年の際にも新型のインフルエンザの発生が判明してからワクチンを製造し供給を開始するまで半年ほどかかりました。ワクチンが接種できる準備ができたのは、すでに本格的な流行が過ぎ去った後、というところも多かったのです。
では、できるだけワクチンの供給を早めるためにはどうしたらよいでしょうか。一つは、ヒトからヒトへの感染性を獲得し新型インフルエンザウイルスとなりうる可能性のあるウイルス株のワクチンを事前に作成し準備しておくこと、もう一つはより時間のかからない製造方法を開発することです。
前者の方策として、これまで日本は鳥インフルエンザA(H5N1)ウイルスを標的とした「プレパンデミックワクチン」を準備してきました。H5N1 ウイルスは、鳥からヒトへの感染が見られるものの、まだヒトからヒトへの感染が容易なウイルスとは言えない段階です。さらに変異が積み重なることで、ヒトからヒトへの感染性を獲得する可能性があると考えられますが、現段階で鳥からヒトに感染が見られるH5N1ウイルスに対するワクチンを「プレパンデミックワクチン」として準備しておいて、もし新型のウイルスがH5N1亜型由来のウイルスだった場合に、少しでも早い段階から、幾らかの防御効果を期待して利用しようというものです。特に、医療関係者や、初動対応、社会機能維持に従事する人を接種対象として想定し、H5N1ウイルスのヒトへの感染状況を睨みつつ、平成18年度からさまざまな種類(系統)のH5N1ウイルスに対するワクチンを作成してきました。しかし、近年、このH5N1 ウイルスのヒトへの感染例が世界的にほとんど見られなくなり、代わりに鳥インフルエンザA(H7N9)ウイルスのヒトへの感染事例が多く見られるようになってきました。そのため、今後はH7N9ウイルスを標的としたプレパンデミックワクチンの備蓄に移行することになっています。
一方で、製造工程の短縮化の方策としては、細胞培養ワクチンの開発・供給体制の整備が進められてきました。従来のインフルエンザワクチンは、ワクチンの素になるウイルス株を、鶏卵を用いて培養して製造してきました。しかし新型のインフルエンザの発生が判明してから全国民分のワクチンを製造し供給し終えるまでに鶏卵では1年半から2年かかってしまうことから、より効率的な製造工程の開発が進められてきました。細胞培養ワクチンは、人工的に培養した細胞を用いて、ワクチンの素となるウイルス株を増やして製造します。2011年から開発と生産体制の構築が進められ、ようやく半年で全国民分のワクチンを生産する体制が整ったところです。
生産体制が整ったならば、先ほどの医薬品の話と同じく、いかに供給し接種に至るかが問題になります。接種が終わる前に流行が過ぎ去ってしまっては意味がありません。効率的に接種を進める仕組みを考えなければなりません。また、国民全員に対してある日一斉に接種できるわけではないので、ある程度優先順位をつけて接種を進めていく必要があります。しかし、2009年の新型インフルエンザ発生時にも、「ワクチンを誰から打つべきか?」という優先順位が議論になりました。対応しなければいけない人から打つべきか?社会機能を維持する業務の人を優先すべきなのか?この国の将来を支える小児なのか?あるいは、感染した時に重症化する可能性が高い高齢者や基礎疾患がある方からなのか?その優先順位を誰が決定するのか?その根拠となる法律は?このような様々な議論がありました。議論は重要ですが、発生してからこのような優先順位をつけた接種を行う枠組みを一から議論していては、ワクチンを打ち始めるのが遅くなってしまいます。さらにはその優先順位に従って接種を行うための手続きにも時間がかかってしまいます。それでは供給が流行に間に合わなくなってしまいます。優先して打つべき方がいるならば、事前に登録をして接種する方法を決めておけば、より早く接種できるかもしれません。
特措法では、「特定接種」と「住民接種」という二つの枠組みが作られました。前者は、新型インフルエンザ対策を担う医療関係者や行政職員のほか、重要インフラ関係業務など、社会機能を維持する業務に従事する者を対象としたワクチン接種の枠組みです。後者は、それ以外の一般住民に対してワクチン接種を行う枠組みです。前者は、対象者の事前登録が進められており、平成29年度末には初回分として約568万人が登録されました。後者は、接種を実施する手続きの整備や、対象者への接種を短期間に迅速に進めるための接種場所の整備や訓練などが行われています。なお、「特定接種」と「住民接種」を組み合わせた接種順位については、新型インフルエンザの発生時に、流行の特性等を見て、基本的対処方針等諮問委員会の意見を踏まえ、政府対策本部において決定されます。このように、危機発生前に、事前に決められることは少しでも事前にきちんと決めて準備しておくことが、危機発生時に迅速に行動を起こすためには欠かせません。さらには、接種を行うための手続きの整備も望まれます。IT技術も活用して、接種対象者に接種順位を通知し効率的に接種場所に導くようなシステムを構築することで、限られたワクチン供給を最大限に生かした、緊急時の迅速な接種が実現できるでしょう。
Ⅲ. 訓練・演習
危機管理のサイクルの中では事前の準備活動に割く時間が大半を占めます。何か危機が起きている時がその活動が一番目立つ時ですが、危機管理のサイクルの中ではわずかな時間に過ぎません。事前の準備は、目立たない活動ですが、最も重要な部分といっても良いでしょう。その中でも訓練や演習は非常に重要です。

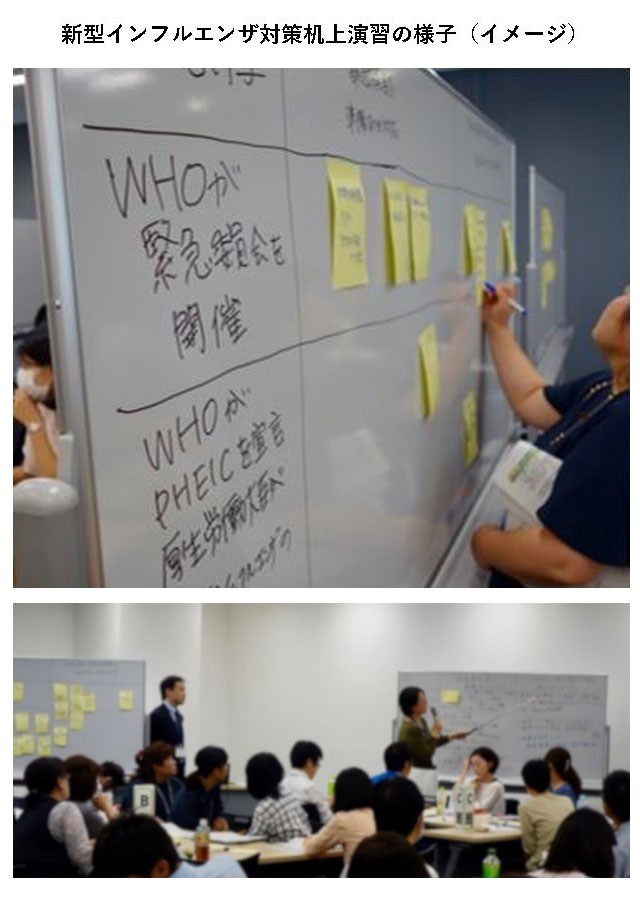
政府は毎年、政府対策本部会合運営訓練(※1)を行なっています。連絡訓練(※2)は、平成28年度からは、全関係府省庁、全都道府県、全指定公共機関、全指定地方公共機関、全市町村が参加する大規模な訓練になっています。自治体や関係機関でも、患者さんの安全な搬送、住民へのワクチン接種、患者増大時の医療機関の対応、施設の使用制限、検疫対応といった訓練が行われています。実動訓練のみならず、発生時の意思決定の判断力を磨く机上演習も重要です。新型インフルエンザウイルスの病原性、毒性等を見極め、流行状況を的確に判断し、リスクに応じた適切な対策を選択していくことが不可欠です。数理モデルやシミュレーションといった新たな技術も意思決定の支援に今後もっと活用されていくことでしょう。これらを活用したより効果的な訓練手法の開発と実践も望まれます。
新型インフルエンザ対策は、医療や公衆衛生に日常的に携わる人たちだけでなく、社会全体で取り組む対策です。訓練や演習の機会を通じて、新型インフルエンザという社会の危機のイメージを共有し、それぞれの役割を認識することも重要です。何かが起きてから関係者と「初めまして」と挨拶をするのではなく、「また会いましたね」と言える、いわゆる「顔の見える関係」を訓練や演習を通じて事前に構築しておくことは、あらゆる危機管理に共通して重要なことです。

訓練は継続的に行なっていく必要がありますが、特措法の存在は強力な推進力になります。特措法の第12条には訓練を実施する努力義務が規定されているからです。これも、2009年後の新型インフルエンザ対策の大きな進歩の一つと言えるでしょう。
※1 政府対策本部会合運営訓練:新型インフルエンザが発生した場合に設置される政府対策本部(総理を本部長とし全閣僚が構成員)の会合を、架空のシナリオに基づいて実際に開催し、政府がとるべき対策等を確認する訓練。
※2 連絡訓練:政府対策本部会合運営訓練に連動させて行われる訓練で、予め決まっている連絡体系に従って、対策本部会合での決定事項等を速やかに関係機関と共有し、有事における連携体制を確認する訓練。
おわりに
これまで、2009年のパンデミックから10年間の進歩を振り返ってみました。特措法を推進力として、2009年の記憶と教訓を忘れることなく、柔軟性を保ちつつ、国家の危機管理として政府一体となった対策が継続的に進められてきたことがわかると思います。諸外国の中でも特に堅牢な仕組みを構築してきたと言えるでしょう。
新型インフルエンザ対策は、季節毎のインフルエンザ対策の延長線上にあります。どんな新しい型のインフルエンザウイルスが出現しようとも、まずは、手洗い、咳エチケット等の基本的な感染防御対策があり、睡眠、栄養等、体調を整えること、そしてワクチン接種と、個人の対策がまん延防止対策の根本となることは変わりません。さらには、インフルエンザに罹った際には、学校や仕事を休み、休養に充てるのが当たり前な社会になることが望まれます。それには個人の意識のみならず、休みを取りやすくするような社会環境の整備も重要でしょう。
新たなインフルエンザワクチンの開発も課題の一つです。現在のワクチンはある一定の防御効果を有するものの、国内で一千万人以上もの患者が発生する流行が毎年生じているのが実情です。しかも、毎年のウイルスの顔つき(抗原性)の変化に対応できないので、毎年流行株に応じたワクチンを製造し接種しなければなりません。顔つきの異なるウイルスにも防御効果を有し、1度打てば何年も効果が持続し、より感染防御効果の高いインフルエンザワクチンができればどれだけ良いことでしょう。世界中がそのようなワクチンの開発に鎬(しのぎ)を削っていますが、実用化にはまだ時間がかかりそうです。
2009年の新型インフルエンザは、インフルエンザ対策の重要性を思い起こさせてくれました。「新型インフルエンザ対策」を「一過性のパンデミック」に終わらせるのではなく、地震への備えのごとく、日々進歩させ、我々の文化の中に刷り込み、継承していく努力は今も続いているのです。