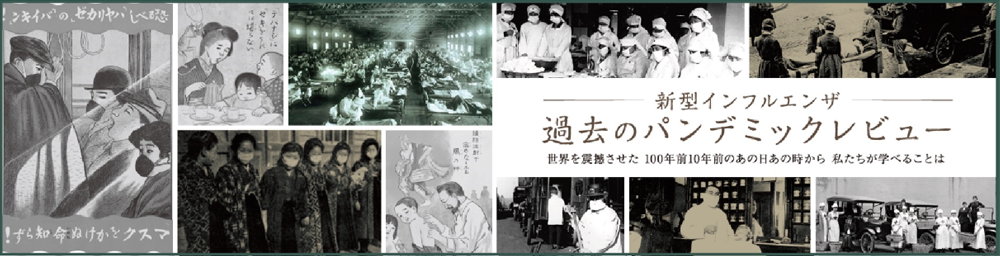
 スペインインフルエンザ(前半)
スペインインフルエンザ(前半)
防衛医科大学校病院副院長(兼)感染症・呼吸器内科
教授 川名明彦
はじめに
2018年は、いわゆる新型インフルエンザの世界的大流行(パンデミック)である「スペインインフルエンザ」が発生してから100年目の年でした。スペインインフルエンザは、科学的に検証しうるパンデミックとしては過去最大のもので、地球規模で膨大な患者と犠牲者を出しました。インフルエンザのパンデミックは、規模の大小はあるものの過去に幾度も発生しており、またこれからも発生すると予想されるため、その対策が進められています。正しい対策のためには、過去のパンデミックを振り返り、その被害の全容や先人たちの取り組みを知ることも重要です。今回は、インフルエンザとパンデミックの歴史を概観し、特にスペインインフルエンザに焦点を当て、2回に分けて解説します。
I. インフルエンザの歴史
1歴史の中のインフルエンザ流行
インフルエンザは、インフルエンザウイルスによって起こる感染症で、北半球の温帯地域では毎冬すなわち12~2月頃に流行します。南半球は季節が逆ですので、寒い6~8月頃に流行します。毎シーズン人口の1割程度の人が感染すると推定されますが、流行は数週間で自然に終息します。このように普段流行するインフルエンザは、季節と連動することから「季節性インフルエンザ」とも呼ばれます。一方、新型インフルエンザのパンデミックは、季節に関係なく出現し大流行します。
インフルエンザと人類の関わりは古く、歴史的な資料の中にインフルエンザと思われる疾患とその大流行の記載を見ることができます。古代ギリシアのヒポクラテス(紀元前460年頃~)は、「ある日突然多数の住民が高熱を出し、震えがきて咳が盛んに出た。たちまちこの病気は広がり、住民たちは脅えたが、あっという間に去っていった」という記録を残しています。これはインフルエンザの流行を記述したものだろうと考えられています 1),2)。
中世のヨーロッパにもインフルエンザと思われる病気の記録が多数残されており、その流行が周期的に現われるところから、16世紀のイタリアの占星術者たちは、星や寒い天候の影響(influence)による病気と考えました。これがインフルエンザの語源とされています 3)。
17世紀、英国の解剖学者で医師のウィリス(Willis T)は「いくつかの村で非常に多くの人が病気になった。成人患者の特徴は、厄介な咳、痰、鼻腔から口蓋、喉にかけての炎症、発熱、渇き、食欲減退、疲労、背中と手足の激しい痛みである。病弱な者、年寄りは死ぬ者も少なくなかった」と記載しています。18世紀、スコットランドの医師アーバスノット(Arbuthnot J)は、ヨーロッパ各国からアメリカ、カリブ海地域まで拡大したこの疾患について「症状はどの地方でも全く同じである」と記しています 4)。19世紀には、インフルエンザの世界的流行が何回も起こった記録があります。1889年12月にサンクトペテルブルクで始まった流行は、翌週までに世界で数百万人に感染し、ヨーロッパだけで約25万人が死亡し、特に乳幼児と老人の死亡が多かったと記されています 4)。
わが国にも、平安時代以降インフルエンザと思われる流行病の記録が沢山残されています。江戸時代にも20回以上の大流行の記録があり、「お駒風」、「谷風」、「琉球風」、「お七風」などと呼ばれました 1)。長崎に渡来する外国人から流行が始まったとする記載もあり、外国との交流が制限されていた時代でも、わずかな人の移動を介して世界的なパンデミックの嵐が東アジアの日本にも到達していたことがわかります。
2インフルエンザウイルスの発見
19世紀末、ドイツの学者ファイファー(Pfeiffer)が患者の鼻咽頭から細菌を検出し、それがインフルエンザの病原体であるとして「インフルエンザ菌」という名前を付け報告しました。その後、この菌はインフルエンザの病原体ではないことが明らかになりましたが、「インフルエンザ菌(Haemophilus influenza)」という名前は現在も使われています。その後インフルエンザの病原体は「菌」よりも小さい病原体、すなわちウイルスであることが判明します。
1931年、米国のショープ(Shope RE)が豚のインフルエンザウイルスの分離に成功、続く1933年、英国のスミス(Smith W)、アンドリュウス(Andrewes CH)、レイドロウ(Laidlaw PP)の3人が初めて人のインフルエンザウイルスの分離に成功しました。このウイルスは後にA型と呼ばれます。1940年にはフランシス(Francis T)とマギール(Magill T)によりB型インフルエンザが、1949年にはテイラー(Taylor RM)によりC型インフルエンザがそれぞれ分離され今日に至ります 5)。
ウイルスは1万分の1mmと極めて小さく、電子顕微鏡を使わなければ観察することはできませんが、20世紀末には、鼻やのどの粘液ぬぐい液を使って15分ほどでインフルエンザと診断できる迅速検査法が実用化し、医療の現場では広く使われています。
II. 新型インフルエンザとパンデミック
1新型インフルエンザとは
A型インフルエンザウイルスは、8つの分節に分かれた遺伝子を持っています。2種類の異なったA型インフルエンザウイルスが1つの細胞に感染すると、その細胞の中で遺伝子が混ざり合い、様々な分節の組み合わせを持ったウイルスが出現します。これを遺伝子再集合といいます。自然界では鳥や豚など様々な動物が固有のインフルエンザウイルスを保有していますので、遺伝子再集合により、人のインフルエンザウイルスが動物のウイルス遺伝子を取り込み、新しいウイルスが出来ることがあります。こうしてできた新しいウイルス、すなわち「新型インフルエンザウイルス」には、人類はそれまで遭遇したことがないため、全く免疫を持ちません。そのため新型インフルエンザは人の間で大流行しパンデミックを引き起こす可能性があります。わが国の感染症法では、「新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザであって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの」を新型インフルエンザと定義しています 6)。欧米ではこのようなウイルスを「パンデミック株インフルエンザウイルス」と称しますが、ここでは新型インフルエンザという言葉を使います。
220世紀のインフルエンザパンデミック
に述べたとおり、有史以来人類は多くのインフルエンザパンデミックを経験しています。20世紀に限定しても、大きなものだけで4回発生しており、それぞれ通称で呼ばれています。すなわち、1918年の「スペインインフルエンザ(インフルエンザA(H1N1) ウイルスによる、以下同)」、1957年の「アジアインフルエンザ(A(H2N2))」、1968年の「香港インフルエンザ(A(H3N2))」、ならびに1977年の「ソ連インフルエンザ(A(H1N1))」です 7)。なお、「ソ連インフルエンザ」は、一旦姿を消したスペインインフルエンザの子孫ウイルスが何らかの理由で復活してきたものと考えられるため、真のパンデミックに含めない見方もあります 8)。21世紀に入ってからは 2009年にパンデミック(インフルエンザA(H1N1)pdm09ウイルスによる)が発生したことは記憶に新しいところです。
アジアインフルエンザ以降のパンデミックについては、別の回で詳しく述べられますので、ここではスペインインフルエンザについて解説します。なお、パンデミックの通称については、「スペイン風邪」、「スパニッシュフルー」など様々な呼び方がありますが、本稿では「スペインインフルエンザ」という言葉を用います。
II. 新型インフルエンザとパンデミック
1スペインインフルエンザとは

スペインインフルエンザは、1918年3月頃から1920年頃まで全世界で流行した、科学的に検証可能なインフルエンザパンデミックの中では史上最大のものです。統計は諸説ありますが、この間、当時の世界人口18億~20億人の1/3以上が感染し、数千万人(概ね2千万人~5千万人といわれます)が死亡し、その致死率(発病者数に対する死亡者数の割合)は2.5%以上と推計されています。この流行は第一次世界大戦の最中に起こりましたので、参戦していた国々の兵士にも甚大な被害をもたらし、戦局にも大きな影響を与えました。
各国はインフルエンザによる戦力の低下を敵国に悟られないようその流行を秘匿しましたが、参戦していなかったスペインでは情報統制が敷かれておらず同国内の流行が広く世界に報道されました。スペイン国王や大臣もインフルエンザにかかったという情報が報じられたことなどから、このパンデミックはあたかもスペイン発であるかのように受け取られ、同国の名が付いたとされています。


スペインインフルエンザ流行の様子を撮影した写真が多数残されています。インターネットで「スペインインフルエンザ」、「スペイン風邪」について画像検索をすると多くの写真を見ることができます。以下にその一部を示しました。多くの患者を収容しきれず講堂のような所で診療する様子や、皆がマスクを着用している様子がうかがえます。
※スペインインフルエンザ流行当時の写真
2スペインインフルエンザはどこで発生したか
スペインインフルエンザが世界のどこで最初に出現したか、明確な証拠はありません。インフルエンザウイルスが発見される前のことですからウイルス学的な確定診断はできませんし、また届出義務のある疾患ではなかったのですから、正確な疫学データがないのはやむを得ません。
スペインインフルエンザにつながる最初の流行としてはっきりした記録があるのは1918年3月の米国であり、ここから流行が始まったとする見方が一般的です。しかし、記録があることと真の発生地は同じとは限りません。特に中国は、アジアインフルエンザや香港インフルエンザが発生し、また鳥インフルエンザA(H5N1)やA(H7N9)ウイルスのヒト感染が最初に報告された国でもあることから、スペインインフルエンザも中国で発生したのではないかとする見解があります。その他、ヨーロッパ(フランスなど)やアフリカ起源とする説もあります。ここでは米国から流行が始まったと仮定して話を進めます。
3米国のスペインインフルエンザ
スペインインフルエンザの流行は1918年3月に米国のカンザス州から始まりました 9),10)。3月といえば季節性インフルエンザの流行がそろそろ終わる時期ですが、この年は春を過ぎてもインフルエンザ患者数は減少しませんでした。当初はインフルエンザパンデミックの始まりに誰も気付きませんが、軍隊や刑務所のように総員数が把握できる集団での大流行や、大規模な自動車工場の労働者が多数欠勤して業務に支障が出るなどの事態が次々と起こるようになると、人々は「普段とは違うインフルエンザの流行が始まった」ことに気付きます。膨大な患者の中には死亡する者も少なからず見られ、米国社会は混乱に陥りました。当時、第一次世界大戦に参戦するため米国からは何十万人もの若い兵士が軍艦に乗り大西洋を超えてヨーロッパの戦場に向かいましたが、その中にはインフルエンザにかかった者も多く含まれていました。こうしてウイルスは4月から5月にかけて米国からフランス、イタリア、ドイツ、スペイン、イギリス、ロシアへと拡散、同年6月頃までにアフリカ、アジア、南米まで拡がり、地球規模のパンデミックになったと考えられています。
この1918年の春に見られた流行をスペインインフルエンザの第1波(春の流行、Spring wave)といいます。第1波は、感染者数は多かったものの、致死率はそれほど高くありませんでした。この第1波は同年夏頃に一旦勢いが低下しました。
1918年9月頃からの流行を第2波、1919年初頭以降の流行を第3波といいます。特に第2波においては肺炎を合併して重症化する患者や死亡者が多かったことが知られています 11)。第一次世界大戦と関連したインフルエンザの悲惨なエピソードが多く残されています。例えば、1918年9月29日に米国ニュージャージー州の港を出港し、同年10月7日にフランスに到着した米国の兵員輸送船「リヴァイアサン号」は、1万1千人程の乗員を載せていましたが、航海中に船内で2千人がインフルエンザを発症し80人以上が死亡しました(下船後も含めると合計約200人が死亡したといいます)。市民の間でもインフルエンザは大流行しました。工場労働者の多量欠勤により産業機能が低下、病院の医師・看護師、電信電話会社員、警察官、鉄道員、ごみ収集者、遺体埋葬業者も多数インフルエンザに罹患し、公共サービスが著しく低下したといいます。一部の家庭では、労働や家事をする体力が残っている大人が誰もおらず、収入も食料も途絶えて家族全員が家から出られなくなり、ボランティアが炊き出しをして食事を届けて回ったといいます 9)。まさに現代の大規模自然災害と似た状況が見られたのです。
第1波に比べて第2波で致死率が高くなった理由はよくわかっていません。ウイルスが人に対し高病原性に変異した可能性や、第2波が本来インフルエンザの流行する寒い時期と重なったことなど、様々な可能性が指摘されています 11),12)。
スペインインフルエンザ流行期間中の米国の被害については多くの統計がありますが、1918年~1919年に全人口の1/4以上すなわち2,500万人以上がインフルエンザにかかり、67万5千人が死亡した(うち「超過死亡」すなわちパンデミックにより例年より多く死亡した人数は44万人)とする記載があります 9)。
その後、米国のスペインインフルエンザの勢いは徐々に衰え、住民の大部分が免疫を獲得するとともに病原性も低下して季節性インフルエンザに移行していきました。そしてこのウイルスは、1957年に次のアジアインフルエンザが出現するまで季節性インフルエンザとして毎年流行し続けました。
【文献】
1) 松本慶蔵,編著.インフルエンザのすべて.株式会社メド・コム,東京,2000.
2) 加地正郎,編著.インフルエンザとかぜ症候群改訂2版.南山堂,東京,2003.
3) 国立感染症研究所感染症情報センター. インフルエンザとは
https://www.niid.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/219-about-flu.html)
4) Mary Dobson,小林 力訳.Disease 人類を襲った30の病魔.医学書院,東京,2010.
5) Taubenberger JK, Hultin JV, Morens DM. Discovery and characterization of the 1918 pandemic influenza virus in
historical context. Antivir Ther 2007; 12: 581-591.
6) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律.第六条7
7) Kilbourne ED. Influenza pandemics of the 20th century. Emerg Infect Dis 2006; 12: 9-14.
8) Beveridge WIB. Where did red flu come from? New Scientist. 1978; 23 March: 790-791.
9) アルフレッド・W・クロスビー, 西村秀一訳.史上最悪のインフルエンザ 忘れられたパンデミック.みすず書房,東京,2009.
10) ピート・デイヴィス, 高橋健次訳.四千万人を殺したインフルエンザ スペイン風邪の正体を追って. 文藝春秋社,東京,1999.
11) Taubenberger JK, Morens DM. 1918 Influenza: the mother of all pandemics. Emerg Infect Dis 2006; 12:
15-22.
12) Morens DM, Fauci AS. The 1918 influenza pandemic: insights for the 21st century.
JID 2007; 195:
1018-1028.