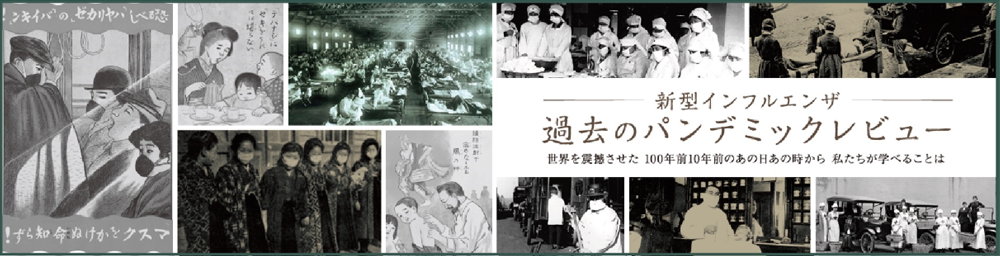
 インターネット社会における「情報開示」と「個人情報の保護」
~2009年関東圏初の新型インフルエンザ患者発生の体験を通して~
インターネット社会における「情報開示」と「個人情報の保護」
~2009年関東圏初の新型インフルエンザ患者発生の体験を通して~
川崎市立看護短期大学 学長
川崎市健康福祉局 医務監
坂元 昇
I 2009年5月20日までの国内外と川崎市での動向
<4月27日> 政府は、北米で流行が拡大していた豚インフルエンザを感染症法の「新型インフルエンザ」と宣言する。川崎市では「健康福祉局健康危機管理対策会議」及び「危機管理推進会議・新型インフルエンザ対策専門部会」を合同緊急開催。
<4月28日> WHOが新型インフルエンザの警戒レベルをフェーズ4に引き上げ、川崎市では「新型インフルエンザ警戒本部」を設置。
<4月29日> WHOは新型インフルエンザ(豚インフルエンザ)について警戒レベルを4から5に引き上げた。その後感染蔓延国の帰国者から疑似症例の報告が各自治体からなされる。
<4月30日> 川崎市は「新型インフルエンザ警戒本部」を「新型インフルエンザ対策本部」に移行し、同日市長を本部長とする第一回会議を緊急開催。役所の相談・衛生研究所検査体制を24時間体制とする。
<5月1日> 隣接する横浜市で全国初の高校生の疑似症例患者が報告される。この高校には多くの川崎市民が通学していることが判明。公表方法をめぐって厚生労働大臣と横浜市長が深夜のマスメディア媒体で非難の応酬を繰り広げ、市民の不安を煽る。早朝横浜市の保健所長に情報交換のため電話するも、保健所長の机が大勢のマスコミのテレビカメラやマイクなどに取り囲まれており会話不能。川崎市でも新型インフルエンザ緊急市民広報を、各区役所管理職の協力を得て川崎市内鉄道7駅で早朝から約2万枚配布(通勤中の市民から先を争うようにビラを取られ、あっという間になくなってしまった)。
<5月6日> 川崎市初の北米からの帰国者の疑似症例を報告(全国的にもまだ珍しかった)、夕刻から深夜に及ぶ記者会見が行われる。
<5月10日> 感染蔓延国からの帰国者で川崎市内追跡調査対象数は1383人となる。また4月27日からの電話などでの相談件数が830件(19日までは2416件)となり、相談者の不安感が強く一人一人の相談が比較的長時間及ぶことや、追跡対象者のフォロー作業など職員の疲弊防止が大きな課題となる。
<5月13日> 川崎市は北米からの帰国者の疑似症例患者に初の入院勧告を行う。簡易検査キットで陽性となり、マスコミ注目の中で検査検体はパトカーの先導で国立感染症研究所に搬送。国立感染症研究所及び市衛生研究所で同時にPCR検査を行ったが陰性となり、簡易検査キット陽性は非特異反応と判断。感染症法に基づく入院を解除した。さんざん振り回された患者や家族への説明に苦慮する。
<5月18日> 夜、新型インフルエンザ対策について医療系団体と緊急会合を行う。診療体制の確保と拡充、発熱外来担当の看護師のために保育園の確保、市が保管している検査キットの配布、備蓄タミフル等について話し合う。
Ⅱ 2009年5月20日(水) 関東圏初症例
<10時頃> 市内高校の複数の生徒(川崎市、横浜市、東京都在住)が米国での教育行事に参加し1週間滞在、19日に帰国の飛行機の中でインフルエンザ様症状を発症(夕方の成田空港検疫の簡易検査キットではA型陰性)との情報が入る。
<14時頃> 当該高校生が市立川崎病院発熱外来受診。
<15時頃> 簡易検査キットでA型インフルエンザ陽性。
<15時50分> 検体を衛生研究所で検査を開始。
<17時30分> 副市長を中心に今後の対応について打合せを行う。医務監が外出中の市長に電話して「かなり疑わしい疑似症例」があることを報告。保健所担当者から家族が疑似症段階での発表を拒否しているとの連絡が入る。疑似症での発表を基本的に行うこととされていたが、高校生のグループ旅行で身元が判明しやすいという特異な背景や、正確で詳細な情報確保のため家族との良好な関係性維持の重要性を鑑み、今回は疑似症例の段階では発表しないことを市長に諮り決定する。
<18時頃> 厚生労働省の担当と都内在住の同校に通うもう一名の疑似症例の対応について電話で相談。確定となったら東京都と同時発表になるとの意見であった。その後、長期戦に備えて着替えなど荷物を取りに一時帰宅する。
<20時40分> 新型インフルエンザのPCR陽性との川崎市衛生研究所からの連絡で、自宅から急きょ役所に戻る。
<21時頃> 「東京都が都内在住の米国帰りの高校生がPCRで陽性と発表」とのテロップがテレビで流れる。それ以前から、川崎市役所にも多くのマスコミ関係者が集まり始め、執務室まで押しかけてくるような騒ぎとなっていた。マスコミ関係者から、「この東京都のケースが川崎市内の高校に通う米国から帰国した生徒であり、川崎市内にも感染している高校生が住んでいる」との情報がインターネットに書き込まれていることを教えられる。川崎市の担当者がそのサイトを確認すると、「米国での公式行事に参加した日本の高校生たちが現地で派手なパーティーをやっており、その中にこの感染した高校生も参加していた」との、高校の実名も含まれるかなり具体的な書き込みがなされていた。この頃からインターネットでこれらの高校生に対する悪意に満ちた批判や中傷の書き込みが増えて行った。厚生労働省担当から東京都が22時から記者会見を行うとの情報がもたらされる。記者から川崎市はいつ記者会見をやるのかと迫られる。
<22時40分> 出張先から緊急登庁した市長に状況の説明を行う。市長自ら記者会見に臨むことにする。マスコミには23時から記者会見を行うと発表する。厚生労働省担当から「東京都は都内在住の患者が川崎市内の高校の生徒であることには触れないのでそのつもりで対応をお願いしたい」との連絡あり。また横浜市内在住の発熱している同校の生徒についてまだ調査が終了していないとの連絡あり。東京都と横浜市との間での調整がうまくできないままマスコミに急かされて記者会見に突入することになってしまった。
<23時15分> 関東圏初症例についての市長記者会見開始。市長が用意した原稿を読み上げ、関東圏での初の感染確定症例であることを説明。その後陪席していた私が患者の現地での行動、帰国便、成田から自宅までの経路について説明を行う。記者会見が東京都に1時間遅れたことに対する批判に満ち満ちた雰囲気の中での会見となった。1時間ほどで午前0時頃市長は退席する。
2009年5月21日(木)
<午前0時10分> マスコミ各社から「患者の帰国後の成田空港からの移動経路についてリムジンバスの会社名や運行時間、座席の位置、乗車していた当該高校関係者の数と座席の位置関係、リムジンバスを降車後に乗った電車について乗車駅・降車駅、列車の運行時間や乗っていた号車番号と位置、降車駅から自宅までの交通手段、家族構成、家族の行動範囲など」細部にわたり明け方まで4時間近く繰り返し質問攻めにあう。インターネットの書き込み内容についても質問された。細かなことを答えられないとその都度、「怠慢だ。調査がいい加減だ。それで市民の健康が守れるのか」との怒号が飛ぶ険悪な雰囲気となった。再度の患者への聞き取りは安静の必要性から医師に許可されなかった。「北米での感染が苛烈を極めている最中にわざわざ米国に勝手に遊びに行って、感染して帰ってきた不見識な高校生」というインターネットによる非難中傷は明らかにマスコミや一般市民の心情に悪影響を与えていることを感じた。また高校生が駅を降りてから利用したタクシー会社については、「川崎市は乗せたタクシー運転手の命はどうなってもいいのか」と、緊急調査を約束させられた。ところが役所が調査をする直前にマスコミが先まわりしてタクシー会社を調べまわり、役所がまだ調査していないことが分かると、「医務監は怠慢でうそつきだ」と言われてしまった。役所から当該駅に乗り入れているタクシー会社に調査依頼を行った。そんなに大きな駅ではなかったが、一昨日の夜大きなトランクを所持した高校生を乗せたというタクシーは現れなかった。風評被害を恐れたために回答を控えたのではと思われた。さらに役所で記者会見をやっている同じ頃に、当該高校を探り当てたマスコミが高校に押し寄せて、校長を取り囲み記者会見が行われていた。校長が泣きながら米国の行事に生徒を参加させたことをわびていたようであるが、役所は翌日の報道で初めて知った。高校にいる記者と役所にいる同じ会社の記者が携帯電話で巧みに連絡を取り合い、役所と高校の説明の違いを巧みに追及していたことになる。つまり役所が「言えない」と頑張っていた内容を、高校が話してしまっていたのであった。その詳細は後日役所を訪問していただいた校長先生のお話などから分かった。厳しい記者会見での追及に慣れていない実直な教育者にとっては無理からぬ話であると思った。
<4時頃> 役所が疑似症の段階で公表しなかったことに対しての説明を求める質問が始まり、9時ころまでだらだらと続いた。
<13時> 川崎市第3回新型インフルエンザ対策本部会議。
<13時50分> 記者会見でこの本部会議の説明を行い、米国での行事に参加していた他都市在住の高校生の情報について細かく聞かれ、川崎市の調査対象ではないと回答するが、怠慢であると批判される。成田空港から横浜に戻ってきたリムジンバスについては、生徒によって便名や時間の記憶が異なり、バス会社に聞いても高校生らしき客は乗せた覚えはないとの回答であった。明らかにバス会社が風評被害を恐れているように思えた。
<14時> 疑似症の段階で発表しなかった件について謝罪を求めるマスコミの要求で記者会見を再開。疑似症の患者でも予防や治療に必要な情報をマスコミに積極的に公表することが基本とされていた。「患者の行動経路を詳細に市民に知らせることは市民の命を守るための“予防”につながるとは考えなかったのか」と激しく追及される。しかし感染症法の2条には「感染症の患者等が置かれている状況を深く認識し、これらの者の人権を尊重しつつ、総合的かつ計画的に推進されることを基本理念とする」と書かれていることへの理解を求め、公表しなかったことについてこの2条の理念と感染者や家族の要望に心情的に配慮した結果であることは認めた。「発表して高校生が精神的に追い込まれて最悪な事態となった時、もし結果的に感染していなかったら役所はどのように責任を取ってくれるのか」と言われたことや、情報を得るためには家族との信頼関係構築が最も大切であることなどから疑似症段階での発表を控えたことを説明する。もちろん家族は本当に感染していたら発表はやむを得ないと言っていたことも併せて付け加えた。最後に議論が責任の取り方に発展し、この件について市長や副市長の了解を得ているのかと追及されるが、現場の責任者の医務監の判断で発表しないことを最終的に決めたことを謝罪する。私も職員もマスコミも昨日から一睡もしていない。ある意味全員が異様な興奮状態になっていた。マスコミも疲労のためか最終的にはうやむやのうちに記者会見は終わってしまった。厚生労働省もちょうど同じ時間、この疑似症の川崎市の対応についてマスコミから激しく攻め立てられていたことを翌日知った。この後、ご家族から「疑似症段階での発表を控えるように役所にお願いしたことはない」とのコメントがあったとマスコミから教えられた。事実かどうかは確かめようもなかった。私はこの点でも一部のマスコミから「うそつき公務員」と呼ばれるようになった。一部の報道で私に対する批判的な記事が書かれていた。特にインターネットの書き込みでは、当該高校に対する激しい非難や中傷や、電話による抗議が激しさを増していた。同時に私に対しては「発表を意図的に遅らせて市民を危険に陥れたうそつき医務監」との非難がインターネットに書き立てられ、役所にも多くの抗議電話がかかってきた。インターネットを見ていた私の息子が内容のすさまじさに驚いて、インターネットは見ない方がよいと私を珍しく気遣ってくれた。
<19時> 厚生労働省の担当から電話があった。「今回の川崎市のことは厚生労働省にとっても本当にいろいろ大変であったが、むしろこれからの感染症対策を考える上ではとても貴重な体験であったと思う。マスコミへの公表のあり方も事態が落ち着いたら真剣に考えて行くべきであろう。ともかくご苦労様でした。」と、ねぎらいの言葉をかけられた。また「今回のことは特異な側面もあるが、混乱を回避するためにはある地域に限った“地域指定”のような対処法も今後必要と思われる」との見解も示していた(これは翌日出された基本対処方針で反映されることとなった)。また夜になって当該高校より休校措置の相談があった。感染者は帰国後まったく登校していないことから医学的には休校は不要であると告げるが、学校へのすさまじい抗議やマスコミが学校に常時張り付いており正常に授業ができる状態にないので休校したいとのことで了解する。22時頃家に帰って40時間ぶりに眠りにつく。
2009年5月22日(金)
川崎市における5月20日からの3日間の電話等の相談件数が2323件となる。政府は「第4回新型インフルエンザ対策本部」の会合を開き、「基本的対処方針」を決める。その中で新型インフルエンザ感染者が発生した地域を、1)感染の初期、患者発生が少数であり、感染拡大防止に努めるべき地域、2)急速な患者数の増加が見られ、重症化の防止に重点を置くべき地域の2つに分けて対策を記載していた。この基本的方針にはこの川崎市での今回の騒ぎが影響を与えたと厚生労働省の担当者から教えられた。
<16時> A新聞社の記者から感染例の公表基準のあり方や患者に対するインターネットなどでの非難中傷について取材を受け、医務監への非難や中傷について記事にしたいと申し込まれるが、公務員なので批判も職務の一環であると断る。
<18時> B新聞社の記者から取材を受ける。当該高校の対応について見解を求められる。「私や役所の対応への批判の取材は喜んでいつでも受けるが、当該高校やご家族等には何の責任もないので、取材は基本的には避けていただきたい」とお願いする。
<19時> C新聞社から取材を受ける。D新聞の記事の中に川崎市が公表を差し控えた案件について、医務監が「インターネットなどで批判がされると子供が自殺するかもしれないと母親が言った」との件について、役所としてD社に抗議したとの話を聞いたが事実かと聞かれる。「記事は確かにそのように書かれているが、仮の話で一般論として述べたことが極端な記事になってしまった。誤解を生むような私の説明にも問題があったことは反省している。ご家族に何ら責任があるわけではない。むしろ被害者であると思っている」と、述べた。初めてインターネット社会の恐ろしさを痛切に感じた。今まで市内で発生した事件をめぐって何度も記者会見の経験がある私ですら足がふるえるような恐怖を感じたので、ご家族や患者そして高校関係者の心中を思うと本当に心が痛む。
Ⅲ その後の経緯
6月25日(木)
市立川崎病院で看護師の集団感染が発生(国内初の大規模医療機関内での従事者の集団感染と言われた)。この頃にはマスコミとの関係性もよくなっており、川崎市の対応について好意的な記事を掲載してくれる。これはマスコミに毎日定時に状況報告や情報交換を行うなど川崎市の積極的な姿勢が評価されていたことによるものであると考えている。
7月17日(金)
厚生労働省から「積極的疫学調査」を来週から止める方向であるとの連絡を受ける。川崎市の新型インフルエンザ発熱相談センターの24時間体制を、この日の24時で終了する。
7月19日(日)
国内の新型インフルエンザの発生が4000人を超えたと厚生労働省が発表する。また川崎市内の新型インフルエンザの感染者は118人となった。すでに通常の医療機関での診療体制が定着されてきていた。
7月20日(月)祝日 最後まで気を抜かず
川崎市内で全国初の新型インフルエンザ感染による“脳症”患者発生が確認される。しかし発表が22日となり厚生労働省やマスコミから対応の遅れを批判される。17日には国から来週から「積極的疫学調査」を止める方向との連絡を受けていたことや、7月に入ってからは、マスコミへの逐一的な対応はすでに止めていたこともあり気が緩んでいたことは否定できない。また長期間にわたる対応で、数少ない行政医師の疲労も激しく、19~20日の休みの日は事務職対応として医師を自宅待機として役所に張り付けていなかった。つまり「脳症」ということの医学的な重大性が理解できていなかったことから、緊急公表を要する事例との判断がなされなかったことによるものである。これは私の判断ミスであった。最後まで気を抜かないという大切な教訓を得た。
7月22日(水)
「新型インフルエンザ(A/H1N1)の国内発生時における積極的疫学調査実施要綱の改定について」の事務連絡が厚労省から来る。5月1日の「暫定版」は廃止され、新型インフルエンザ騒ぎも徐々に終息に向かいつつあった。患者は増えてはいるが、冷静さは徐々に取り戻しつつあった。
IV 最後に、今後求められる対応
今から60年も前、私がまだ小さかった頃、広島で被爆した後遺症の再発で体調を崩していた父が結核を患い10年近く入退院を繰り返していた。幼稚園に入るのを嫌がられただけではなく(入園できるお金もなかったが)、わが家の前を鼻と口を押えて小走りに通る人もいた。父は亡くなる間際まで、子供たちに辛い思いをさせたことを悔いていた。でも父の責任ではないことは私たち子どもにはよく分かっていた。感染症を個人の責任と考えることは感染症対策を遅らせ、非科学的なものにしてしまうことを強く感じている。これが私の感染症に対する原点である。
私が保健行政の道に入ってから体験した感染症のアウトブレイクとしては、1996年3月に感染牛の牛肉による「クロイツフェルト・ヤコブ病」の発生を英国政府が明らかにした時である。当時厚生労働省から感染症の勉強のためロンドン大学に派遣されていた。ロンドンのハンバーグ店から客がいなくなってしまい、マスコミは連日政府攻撃を繰り広げていた。日本に帰国直後の同年、7月に大阪府堺市でO157による大規模な集団感染が起こった。当時保健所長をしていた管区内でも患者が発生し、不安に陥った市民からの問い合わせに忙殺された。また2001年に立法府である国会がハンセン病問題に対して謝罪決議を行い、感染症に対する非科学的な差別問題への猛省を促されることとなった。2003年には中国を中心にSARSの感染流行が起こり、初の新感染症に指定された。川崎市において国内初とされた疑い症例が公表され、流行地域から帰国した有症患者に対する診察を忌避する問題や医療従事者の補償問題、流行地域からの帰国者であることを隠した市内のホテル宿泊者から疑い症例が出たことなど川崎市でも大きな混乱が見られた。流行地域の中国に工場など進出させている企業が川崎市内に数多くあることを初めて知った。そして今回の2009年の新型インフルエンザのパンデミック(大流行)である。
さらに2017年に川崎市内の幼稚園において園児が相次いで死亡するという事件が起こった。「川崎で得体の知れない感染症が流行」という根拠のない情報、当該幼稚園関係者への批判的な書き込み、それらを基にしたマスコミの取材合戦、さらには関係のない周辺の幼稚園が休園に追い込まれるなど、最近の感染症のアウトブレイクではインターネットやSNSなどによる情報拡散が無視できなくなってきている。
感染症に限らずインターネットやSNSの根拠のない情報拡散は時代とともにますます膨張拡大し、特に感染症のアウトブレイクの場合、これらが市民を動揺させ不安に陥れ、時として個人への不当な差別や中傷につながり、結果として冷静で科学的な対策を阻害するものとなりうる危険性が益々大きくなっている。 これに対する対策として、インターネットやSNSで流れている情報をむしろ積極的に公表して、その一つ一つに対して丁寧に科学的根拠や事実関係がないことを説明する必要があると思う。実際の記者会見で何度かこれを試してみたが、険悪な雰囲気であった記者会見の場が和むなど効果は大きかった。記者自身もこれらの情報に不安を感じていることが分かった。役所はインターネットやSNSの情報を「低俗でいい加減なものとして」言及することを避ける傾向がある。しかし過去の経験から、避けようとする役所の姿勢が、逆に市民やマスコミに役所が何か隠しているかもしれないとの憶測や不安を招き、さらに根拠のない情報が拡散してゆくという悪循環を生むことを実感した。市民を不安に陥れる可能性のある情報が流れていることをしっかり受け止め、これに目を背けず淡々と冷静に対応する姿勢を役所が自ら示すことが重要であると感じている。今後の感染症アウトブレイクにおけるリスクコミュニケーションのあり方の一つとして検討する必要があると思う。